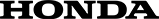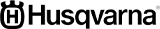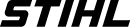「庭を芝生にしたいけど・・・」と迷っているあなた、
「何から始めたらいいの?」という芝生初心者のあなたに!
芝生の素晴らしさと、お庭づくりのノウハウを分かりやすくご紹介します。

芝生は環境にやさしいことでも注目されています。
水分を含む芝生は周りの熱を吸収する効果があるため、庭や屋上などに張れば暑さを軽減し、夏を快適に過ごすことができます。クーラーをあまり使わずに済むので省エネになり、微力ながらヒートアイランド対策にも。雨が降っても泥でグチャグチャにならず、風が吹いてもホコリがたたない。そんな人間にやさしい環境が作れるのもメリットのひとつと言えるでしょう。

清々しく広がる緑、心落ち着く色彩感。生命力あふれるグリーンの芝生は人の心を豊かにし、家の表情を明るく演出します。しかし、芝生の魅力は視覚的な開放感だけにとどまりません。フカフカの芝生はクッション性が高く、転んでも安心なので子どもたちの遊び場には最適と言われています。
裸足で歩いたり、ゴロゴロ寝転がったりと、自然を肌で感じることができるのも、現代の子どもたちにとっては貴重な体験なのではないでしょうか。

また、芝生の上で運動するのは、とても気持ちがいいもの。お母さんはヨガやストレッチ、お父さんはゴルフのパットやスイングの練習、子どもたちはサッカーや野球の練習と、家族それぞれが思い思いに体を動かすことができます。とくにパットの練習は芝生の上でやると臨場感たっぷり。俄然やる気が出てゴルフの腕が上がるだけでなく、日頃から運動不足のお父さんの健康管理にも一役買ってくれるはずです。
![]()
緑のじゅうたんとも呼ばれる美しい芝生を育て、維持していくためには、まず芝生に適した環境選びがとても重要になります。芝生を植える場所はできるだけ日当たりが良く、風通し、水はけのよい場所を選びましょう。また、芝生を張るのに適した時期は、芝の活性がはじまる3月~5月になります。梅雨前に芝張りは終わらせておきましょう。

| 日当たり | 樹木や家屋などの日陰を避けましょう。生育不良の原因になります。 |
| 見通し | 風通しが悪い場所は、害虫や病気が発生しやすくなります。 |
| 水はけ | 水たまりができるような場所は、根腐れなどを起こす原因となります。 |
日当たりが良い場所が芝生に適するのは、芝草の性質が日向を好む植物だからです。
1日3時間以上の日射は必要と言われていますが、芝草の種類によっても耐陰性は異なります。
![]()
芝草は大きく夏芝(暖地型芝草)と冬芝(寒地型芝草)の2つに分けることができます。東北地方以南では夏芝、北海道では冬芝が適しています。芝草として用いられる種類に限定して夏芝と冬芝を比較すると、以下のような特徴があります。(大まかに比較しての違いですが、種によっても異なり、例外もあります。)

- 耐暑性が強い
- 耐寒性が弱い
- ほふく茎のよく発達するものが多い
- 発芽に日数を要し、発芽率が低い
- 葉が硬め
- 草丈はあまり高くならない
- 病害に比較的強い

- 耐暑性が弱い
- 耐寒性が強い
- ほふく茎はないか、あっても生長が遅い
- 発芽が早く、発芽率が高い
- 葉が柔らかめ
- 草丈が高くなるので、頻繁な刈り込みが必要
- 病害に弱い
夏芝でつくられている芝生に、冬芝の種を蒔く方法を冬季オーバーシーディングといいます。芝生の上にさらに芝草を播種(はしゅ)することをオーバーシーディングといいますが、常緑化を目的とした場合は傷んだ芝生を補修する場合と区別するため「冬季」という言葉をつけます。毎年播種する手間がかかりますが、高温多雨の時期に冬芝を維持するよりは楽な方法です。
5~6月頃には冬芝の生育を抑えて、夏芝を復活させるような管理が必要になります。この作業をトランジッションと言います。
![]()

芝生の植え方には、切り取った芝生を敷く方法(張芝)、ほぐした芝生やポット苗を植える方法(植芝・播芝)、種子を播く方法(播種)が挙げられます。
植芝や播種という方法は、芝生化に時間がかかるため、家庭用の芝生化の方法としては、張芝が一般的です。
- 張芝:
- 正方形や長方形に切り取られた芝生を敷き詰めていく方法。ホームセンターなどでも売られていますので、手軽に芝生がつくれます。
芝生化の期間の目安:約2~3か月 - 植芝:
- 溝や穴を掘って植え付ける方法を植芝といいます。校庭緑化などで行われている鳥取方式もこのような方法の一つで、ポット栽培された苗を植え付けています。
芝生化の期間の目安:約1年 - 播種(はしゅ):
- 芝生の上に種を蒔く方法。冬芝の場合、9~10月頃に播種します。5~6月頃も適期です。
芝生化の期間の目安:約3か月
![]()

一言で張芝といっても、張り方には種類があります。すき間なく敷きつめる「平張り(ベタ張り)」と3~4cmのすき間をあけて張る「目地張り」といわれる方法が一般的な張り方になりますが、仕上がるまでの時間と、苗芝にかかるコストが張り方によって異なりますので、目的にあった張り方を選びましょう。
- 平張り(ベタ張り):
- すき間なく芝を並べて張っていく方法。苗芝を多く必要とするため、費用的にはかかりますが、すぐに芝生を楽しめます。家庭用には、短期間で色鮮やかな芝生を楽しめる平張りがおすすめです。
- 目地張り:
- 苗芝の間隔を3~4cm程度あける張り方で、すき間には目土をいれていきます。すき間部分の芝の生育を待たねばならないため、芝が均一になるまで3~4か月程度かかりますが、苗芝は全面積の8割程度ですむため、平張りに比べるとコストがかかりません。
その他にも、一条張りや市松張りといった種類がありますが、芝生の完成までに1年以上かかるため、家庭用には不向きです。
芝生を張る前に、まずは芝生に適した環境と場所を選びましょう。
![]()
- 1:芝生を健やかに育てるために、生育を妨げる雑草や石などをしっかりと取り除きます。
- 2:芝生の根が張る20~30cm程度の土を掘り起こし、肥料を混ぜてよく耕し、板やトンボなどで土の表面を平らに均します。
凹凸がない状態まで丁寧に整地し、しっかりと土を踏みこみましょう。
土の表面に勾配をつけて水が溜まらないようにしたり、水はけを良くしましょう。
よく踏まれる所や透水性の悪い土壌の場合には、必要に応じて多孔質の土壌改良材を混合したりします。
芝を張る面積や、芝生化したい時期によって、芝の張り方を決めましょう。
![]()
芝張りは、3~5月の春先が最適です。日当たり、水はけ、風通しのよい場所を選んで芝張りを行います。

一般的な平張り(ベタ張り)の場合。
- 1:苗芝をすき間なく並べます。
- 2:目地が十文字になると、雨で目土が流れやすくなるため、
レンガのように目地が揃わないように並べます。 - 3:並べ終えたら、軽く踏みつけて土に馴染ませましょう。
![]()
- 1:苗芝のすき間(目地)を、つなぎ目が隠れるように目土をかけます。
- 2:板やトンボなどで、苗芝が少し隠れる程度の量に均したら、
竹ぼうきなどで目土を芝全体にすり込むように凹凸をなくします。 - 3:苗芝と床土が密着するように、再び軽く踏み込みましょう。
![]()
芝の乾燥を避けるため、霧状の水を全体にたっぷりとまきましょう
新芽が生えそろうまで1か月程度、しっかりと根付くのに3か月程度は、なるべく芝生を踏まないようにしてください。
養生期間中は、目地や目土が乾いてきたら水やりをしましょう。
また、芝生の表面に凹凸がある場合は、目土を入れて平らにしましょう。凹凸を放置すると、水はけが悪くなり根腐れなどの原因になります。
![]()

芝生はこまめに刈りましょう。芝刈りには、高さを抑える、表面を平坦にするなどの目的があります。高く伸びてから急に低く刈ると葉が無くなって枯れてしまうので、1回で刈り過ぎないように注意が必要です。
刈る長さの目安は、葉先から1/3以下程度にするのが原則です。日本芝は4~5cmくらい、西洋芝は6cmくらいになったら刈りこみます。西洋芝は暑さに弱いので、日本芝よりは少し長めがいいでしょう。
刈り込みの方向は、縦、横、対角線と毎回方向を変えることで、刈りムラなく仕上がります。芝刈り後は、竹ぼうきなどで掃除をして、刈りカスを残さないようにしましょう。
芝刈りの頻度は、夏は毎週1回、春と秋は月に1~2回するようにしましょう。
芝刈機は安全性の高い機器ではありますが、刃を持っていますので、誤った使い方をしたりふざけて動かしたりすると怪我をすることがあります。使用者はもとより、現場付近にいる子供などにも危険性を周知し、安全な使用に心がける必要があります。
◆芝生が伸びすぎてしまったら◆
1回で短く刈ってしまうと、芝の茎のみになってしまい、芝が弱ってしまいます。
芝刈りを複数回で徐々に刈っていくようにしましょう。
![]()
芝の葉が巻きはじめると水不足のサインです。春なら、晴天が続いた場合は1週間に1回程度、夏は晴天が続いた2~3日に1回、たっぷりと水をまきましょう。地中まで届くように、しっかりと水量を与える方が効果的です。
芝生の広さがある場合は、スプリンクラーを使用すると便利です。秋・冬は月に1~2回程度の頻度で水をまきましょう。
![]()
雑草は、こまめに抜くようにしましょう。素手やカマなどを使い草取りをしてください。
芝生専用の除草剤や、芝生を枯らさずに雑草だけを枯らす選択性除草剤も活用しましょう。
![]()
密生した美しい芝生を維持するために、6月~9月の生育期は毎月1回、芝刈りの後に行いましょう。
この期間に施肥を行うのが効果的です。
芝生全体に、まんべんなく肥料を散布していきます。肥料をまいた後は、必ず水やりを行いましょう。
植物の生育に必要な窒素、燐酸、カリウムなどの養分を肥料の形で施用します。
初心者には芝生用として市販されている化成肥料を用いるのがよいでしょう。
![]()
芝を踏みつけることによって劣化した通気性や、透水性を回復させるために穴あけを行いましょう。
ホームセンターなどで販売されている人力用の穴あけ器を用いることができます。
通気性や水はけ、水分の浸透を促進するために、芝生に穴をあけて、目土をすり込むようにいれていきます。
タテ・ヨコ10cm間隔で、ローンスパイクなどを用います。
![]()
芝生の上から土を掛ける作業を目土(めつち)といいます。
植え付けた時に行う他、年に1~2回目土を行うことが芝生の生育には望ましいです。
目土によって根や茎の発達を促し、表面を平らにするなどの効果があります。
![]()
誰もが憧れる緑のじゅうたん。心からリラックスできる芝生の庭は、まさに"憩いの場"と言えます。お庭に芝生があれば、そこはおしゃれなガーデン。テーブルやイスを庭に出して家族でバーベキューをしたり、お友達を呼んでホームパーティを開いたりと、コミュニケーションの場としても最適です。
芝生の上では誰もが心を解きほぐされ、気持ちよく食事や会話を楽しめるはず。
いつもと違う空間での食事は、心のリフレッシュにも繋がるのではないでしょうか。
![]()
また、芝生の上で運動するのは、とても気持ちがいいもの。
お母さんはヨガやストレッチ、お父さんはゴルフのパットやスイングの練習、子どもたちはサッカーや野球の練習と、家族それぞれが思い思いに体を動かすことができます。とくにパットの練習は芝生の上でやると臨場感たっぷり。俄然やる気が出てゴルフの腕が上がるだけでなく、日頃から運動不足のお父さんの健康管理にも一役買ってくれるはずです。

![]()
庭の芝生は小さなドッグランとして使うのもおすすめです。リードなしで思いっきり走り回れるので運動不足を解消でき、やわらかい芝生は痛めやすい肉球の保護にも役立ちます。これならワンちゃんも大喜び!
また、家族と一緒にペットを遊ばせることで、家族間のコミュニケーションを図れるのも魅力のひとつ。ペットのしつけ方や、どのような遊びが好きなのか、など、一緒に考えることで会話がどんどん広がっていきます。